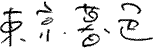
|
|
曲名 |
公表作品 |
作詞者 |
作曲者 |
| 025 |
東京暮色 |
『名前の無い君の部屋』 |
阿久悠 |
及川恒平 |
|
  |
|
|
Em B7 ≒ Em
空に夕月 かかれば お酒を のみ
Am Em B7 Em
年の数程 グラスを 並べて みる
G C D7 G
もう 涙 を 流す ひまも
C D7 Bm Em
ないと思い 歌ったら 溢れる様に 流れて来た
B7 ≒ Em ≒
やっぱり まだ 悲しいんだよ
Em B7 ≒ Em
紙を 一枚 もらって 手紙を 書き
Am Em B7 Em
妙に気どった 言葉に 笑い 出した
G C D7 G
別れた 人 思い出 して
C D7 Bm Em
愛という字 並べたら 段々遠く なって行った
B7 ≒ Em ≒
気持ちなんて 分りは しない
Em B7 ≒ Em
長い睫毛の 女は 夢二の よう
Am Em B7 Em
頬のやつれが 少々 気にかかる よ
G C D7 G
無口 同志 ボツリ ポツリ
C D7 Bm Em
言葉交し いたけれど 芝居のようで やめちまった
B7 ≒ Em ≒
さびしいのは おたがいさまさ
Em B7 ≒ Em
街の灯りは まさしく 東京の 灯
Am Em B7 Em
小手をかざして 見つめて ため息 つく
G C D7 G
この どこかに 帰る けれど
C D7 Bm Em
待ってくれる 人もない もう暫く 歩いていよう
B7 ≒ Em
少しは 今 気分が いいよ
|
|
いつのまにか流れができていて、
ぼくがその中にいることに気がついたのはずいぶん流されたあとだった。
レイブラッドベリの「十月は黄昏の国」をご存知だろうか。
内容はどんな関係もないものの、黄昏の国を頭の中に作り上げていたぼくにとって
「黄昏の国の天使」という自作詞をやめて
「東京暮色」という歌として認識しなおすのは無理があったと、今では見とめざるをえない。
新生ベルウッドレーベルの一応の担い手として、どんな形にせよ、注目される歌、
ようするにヒット曲を出さなければいけなかったのだ。
「作詞家」及川の実績は出発の歌、一曲のみ。
六文銭での曲作りはアマチュアの延長にすぎないと、評価されていたのだろう。
今となれば、ぼくはそれでなんの不満もないし
六文銭を評価してくれていたファンの人だって、
べつに「全国区」になってほしいなんて特別に考えていなかっただろう。
しかし一種の企業戦略の中に所属していた事務所、そしてぼくは入っていったのだった。
|
 |
結果は惨敗。
ぼくのソロとしてのシングル第一弾「雨がふりそうだなあ」は、
様々な戦略をしかけたにもかかわらず、小ヒットに終っている。
そして第二弾がこの歌であった。
どういういきさつで自作詞がけずられてプロの作詞家に
新たに発注することになったのか、「タレント」であるほくは、実際カヤの外であった。
とはいえ、その流れを受け入れたのは、ほかならぬ自分なのだ。
責任転嫁の意思はまったくないし、今はただの思い出話として読んでいただきたい。
勿論、前回の失敗をとり返すべく、会社は全力投球したのだった。
しかしそれにしてはいかにも頼りない「タレント」だった。
レコードキャンペーン、取材をすっぽかしたわけではないし、
それなりに作り笑いをしながらだとしても、与えられた仕事をこなしていたのは本当だ。
ベルウッドに在籍するほかのほんとうの意味での「タレント」が、
日の目を見る時がすこしでも早くなればと、ぼくにとっては、それが夢だった。
この言いぐさが図々しいといわれれば、言い訳けだったと言い換えよう。 |
 |
さてこの「東京暮色」。
流石と言っていいだろう。
阿久さんの時代をとらえる感覚は、フォークジャンルとしては数少ない、
有線でリクエストされる歌としてデビューさせたのだった。
勿論、編曲の国吉も新人アレンジャーとしとていい仕事をしている。
あとはぼくが新人らしく、
身を粉にしてキャンペーンの全国行脚を全うすればいいだけだったといえる。
そう、ぼくはできなかった。
冒頭にあげた「十月は黄昏の国」を、ここではその理由にしておく。
ほんとうは、これは理由の、それもあまり大きくはないひとつにすぎない。
その時体験した阿久さんの時代をジャスとミートしていた作詞家としての姿など、
書くことはまだたくさんある。
きっとつづきは、またいきおいでいつか書くことになるのだろう。 |
|
  |
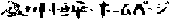
Copyright©2001-2003 Kouhei Oikawa(kohe@music.email.ne.jp)
|